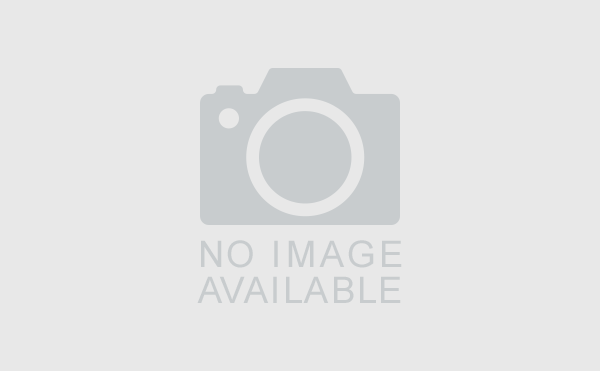検認とは
検認とは、遺言書の形状や日付、署名など、検認日時点での遺言書の内容を明確にすることです。検認手続きをすることにより、検認日以降の遺言書への偽造や変造を防止することが出来ます。
なお、検認を経たからといって、その遺言書が絶対に有効である、というものでもありません。あくまで、検認日時点の遺言書の状態を確定させるだけの手続きです。
検認手続きが必要な遺言書
検認手続きは、遺言書の偽造や変造を防止するために行われます。よって、偽造や変造が行われる可能性のある遺言書は、検認手続きが必要です。
具体的には、自筆証書遺言(自筆証書遺言書保管制度を利用したものを除く)と秘密証書遺言です。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、悪意を持った相続人が、遺言書の内容を追記したり書き換えたりすることが可能です。偽造や変造された遺言内容は、遺言者の真意とは違ったものになりますので、偽造・変造は許されるべきものではありません。
また、検認手続きを経ずにこれらの遺言書で遺言執行したり、家庭裁判所以外で遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられることもあります。
なお、自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言は、法務局(遺言書保管所)でデータとして保管されており、遺言書原本ではなく遺言書情報証明書で相続手続きを進めることになります。遺言書情報証明書を偽造・変造することは出来ませんので、検認が不要となります。
同じく、公正証書遺言の場合も、公正証書を偽造・変造することは出来ないことから、こちらも検認が不要となります。
自筆証書遺言書保管制度については、「自筆証書遺言書保管制度について」をご参照ください。
検認手続きの流れについて
検認手続きの流れは以下の通りです。
・遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などの必要書類を用意する。
・家庭裁判所に検認を申し立てる。
・家庭裁判所から相続人全員に検認期日を知らせる通知が届く。
・家庭裁判所で検認に立ち会う。
・家庭裁判所から遺言書を返却してもらい、検認済証明書を申請する。
遺言書の保管者または、遺言書を発見した相続人は、遺言者が亡くなってから遅滞なく家庭裁判所に検認の申し立てをしなければなりません。
申し立てる家庭裁判所は、遺言者が亡くなった時点の住所を管轄する家庭裁判所です。
遺言書1通あたり800円の収入印紙と、連絡郵便用の切手代がかかります。
まとめ
・検認とは、遺言書の偽造・変造を防止するためのものです。
・自筆証書遺言書保管制度を利用していない自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、検認手続きが必要です。
・検認手続きを怠ると、過料に処せられる可能性もあります。