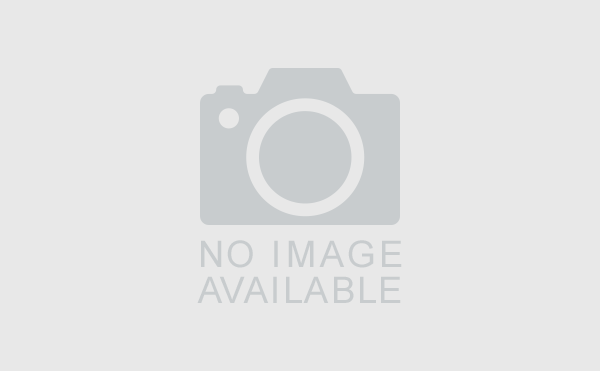遺言書を作成したほうがいい人、作成しなくてもいい人
「遺言書を作成するべきなんだろうか…」ふと考えることがあるでしょう。
そこで、今回は遺言書を作成したほうがいい人・作成しなくてもいい人を紹介します。
もちろん、これらに当てはまった人は、絶対に遺言書を作成しなければならない、というわけではありません。しかし、遺言書を残しておくことで家族(相続人)の負担が減ることも見込まれることから、弊所ではオススメしています。
多くの人は、自分が亡くなったときに相続人の間で争いは起きてほしくないと考えるでしょう。遺言書を作成することにより、相続争いが発生する可能性を下げることが出来るかもしれません。
遺言書を作成することは、あなたにしか出来ません。
遺言書を作成したほうがいい人
子供のいない夫婦で、配偶者に全てを相続させたい人
子どもがいない夫婦で、夫婦どちらかが亡くなると、配偶者に財産が全て相続されるとは限りません。
例えば、遺言書を残さずに夫が亡くなった場合、亡夫に子・父母・兄弟姉妹(甥姪)がいなければ、配偶者(妻)が亡夫の財産を全て相続します。
逆に言えば、亡夫に子・父母・兄弟姉妹(甥姪)がいれば、これらの人が配偶者(妻)とともに相続人になります。
亡夫が遺言書で『相続財産は全て配偶者(妻)に相続させる』と記載していれば、配偶者(妻)が相続財産を全て取得することが出来ます。
しかし、遺言書を残していなかった場合、配偶者(妻)は子(特別代理人)・亡夫の父母・亡夫の兄弟姉妹(甥姪)と遺産分割協議をしなければなりません(子がいる場合は、利益相反行為になるため、特別代理人と遺産分割協議をすることになります)。
そこまで親しくもない間柄の人と遺産分割協議をすることにもなりかねず、相続争いにも発展しかねません。
よって、自分に父母や兄弟姉妹がいる場合は、配偶者のために遺言書の残しておくほうがいいでしょう。
内縁の配偶者や子の配偶者など、相続人でない人に財産を残したい人
遺言書を作成していないと、基本的に相続人以外には相続させることが出来ません。よって、内縁の配偶者や子の配偶者、お世話になった友人や法人などの相続人でない人に相続させたい場合は、遺言書を作成する必要があります。ちなみに遺言書には『相続させる』ではなく『遺贈する』という書き方をします。
いくら内縁の配偶者と実質的に夫婦の実態があったとしても、被相続人に父母や兄弟姉妹がいれば、これらの親族が相続人となります。そして、内縁の配偶者には財産を残してあげることが出来ません。
また、子の配偶者が献身的に介護や世話をしてくれるケースもよくありますが、遺言書を作成しておかないと、お礼として財産を残してあげることも出来ません。
遺言書で法人に遺贈することも出来ます。世のため人のために活動している法人に、自分の財産の一部を使ってほしいと思う人もいるでしょう。
上記のような悩みを持つ人は、遺言書の作成で解決できると思います。
再婚しており、前の配偶者との間に子がいる人
もし遺言書を作成していなければ、遺産分割協議を行うことになります。遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければなりません。前の配偶者との間の子も相続人になりますので、この子も遺産分割協議に参加することになります。
ここで問題となるのが、現配偶者(および現配偶者との間の子など)と前配偶者との子に面識がないケースも多く、ほぼ初対面で遺産分割協議をすることになりかねないことです。
現配偶者は、被相続人が亡くなったことの悲しみのなか、会ったこともない被相続人の前配偶者の子と話し合いをしなければならないのです。大変苦労すると思います。
そこで、あらかじめ遺言書を作成しておくことで、相続をスムーズにすることが出来ます。前配偶者との間の子に相続させない旨の内容にもすることが出来ます(ただし、遺留分の問題は残ります)。
このように、相続人同士が顔も名前も知らない関係性であれば、遺言書の作成をすることにより相続人の負担が大きく減ることになります。
相続財産に偏りがある人
相続財産は、人それぞれです。相続財産のうち、ほとんどが現預金の人もいれば、不動産が多くを占めている人、多数の高級自動車を所有している人などがいます。
ここでは、例として被相続人Aさんは、時価2,000万円の不動産と現預金200万円を残して亡くなったとします。相続人はAさんの子であるBさんとCさんです。
遺言書がなければ、BさんとCさんで遺産分割協議を行うことになります。
Bさん「うちは家計が厳しいから、現預金200万円と不動産900万円分が欲しい」
Cさん「いやいや、それは公平じゃないから、2人とも現預金100万円と不動産1,000万円分にしようよ」
Bさん「どうしても現預金が欲しいんだ。不動産800万円分でいいから現預金200万円にしてほしい」
Cさん「こっちは不動産なんて要らないんだよ。今後管理するのにもお金がかかるしね」
Bさん「うちだって不動産は要らない!売るにしたって不動産屋への手数料もかかってもったいないだろう」
このように、なかなか協議が終わらないこともよくあります。
Aさんが遺言書を書いておけば、BさんとCさんも納得して円満に相続出来るかもしれません。
現預金や換価性の高い株式、投資信託などなら、すぐに現金化して相続人が平等に相続することが出来るでしょう。しかし、換価性の低い不動産がある場合は、スムーズな相続が出来ないかもしれません。
なお、不動産などの換価性の低いものが相続財産に含まれている場合は、「遺産の分割方法」もご参照ください。
相続人のなかに、連絡が取れない人がいる人
前述の通り、遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。しかし、相続人の中に、連絡が取れない人がいると、いつまでたっても遺産分割協議を行うことで出来ません。
数年、十数年もの間、連絡を取っていない相続人がいるのでしたら、遺言書でその相続人以外の相続人に相続させる旨を記載しておくことにより、相続手続きが円滑に行われることになるでしょう。ただし、この場合も遺留分の問題が出てきます。
連絡をずっと絶っていたのに、遺産だけほしいというのは、虫がいい話なのかもしれません。しかし、法律上では相続人に違いありませんので、今のうちに遺言書を作成し、対策を講じておくことも有用です。
遺言書を作成しなくてもいい人
相続人は配偶者のみ、子1人のみなど、相続争いが発生する見込みのない人
相続人が配偶者のみの場合は、配偶者が全てを相続するため、遺言書を作成する必要はないでしょう。ただし、子や被相続人の父母、被相続人の兄弟姉妹およびこれらの代襲相続人がいないことが前提です。
また、相続人が子1人の場合も、その子が全てを相続しますので、遺言書の作成しなくてもいいでしょう。しかし、子が2人以上になると、相続争いの可能性が出てきますので、場合によっては遺言書の作成を検討しましょう。
このように、相続人が1人だけのときは相続争いが発生し得ないので、遺言書を作成しなくても問題ありません。
ただし、相続人以外の人に遺贈したい場合は、遺言書を作成しなければなりません。
相続財産が預貯金などの換価性の高いもののみで、極少額の人
相続財産が預貯金などの換価性の高いもののみの場合は、不動産のように相続財産の押し付け合いは発生しないでしょう。また、極少額の場合は、相続人も多くを相続財産の多くを相続したいと主張することも少ないことが予想されますので、わざわざ遺言書の作成をする必要性はあまりないと思われます。
しかし、遺産分割事件の約8割は、相続財産5,000万円以下で起きていますので、一般家庭でも相続争いは十分に起こり得ます。
もし少しでも不安があるようでしたら、遺言書を作成することにより安心につながるでしょう。
まとめ
・多くの人が、遺言書を作成したほうがいい人に当てはまると思います。
・遺言書は、自分のためだけではなく、相続人(家族)