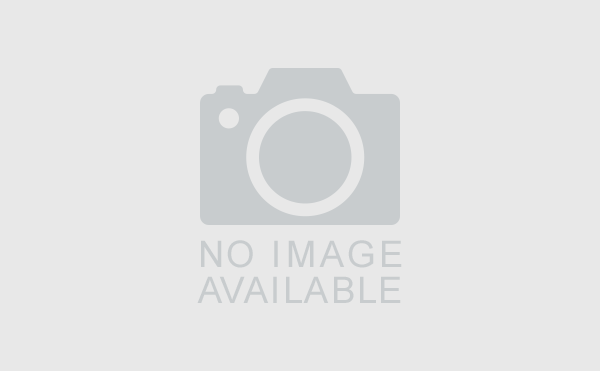自筆証書遺言書保管制度について
今までは自筆証書遺言書を作成した場合、遺言者(または遺言執行者や親族など)が遺言書を保管しなければなりませんでした。主に自宅で遺言書を保管している遺言者が多かったのですが、自宅で保管すると紛失や、遺言者以外の人が破棄や改ざんを行うなどのリスクがありました。
そうしたなか、令和2年7月に自筆証書遺言書保管制度が始まりました。自筆証書遺言書保管制度とは、法務局(遺言書保管所)が自筆証書遺言を保管するという制度です。
自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言書保管制度とは、作成した自筆証書遺言書を法務局(遺言書保管所)で保管してもらえるサービスです。
名前の通り、自筆証書遺言書しか保管されないので、公正証書遺言書や秘密証書遺言書は保管してもらえません。
今までは、作成した自筆証書遺言書を、主に自宅で保管するか、銀行の貸金庫で保管するかだったものが、新たな保管先として法務局(遺言書保管所)という選択肢が増えました。
法務省の自筆証書遺言書保管制度のページはコチラです。
自筆証書遺言書保管制度のメリット・デメリット
メリット
・法務局(遺言書保管所)で保管するため、紛失や改ざんなどのリスクがありません。
・検認手続きが不要となり、すぐに遺言執行をすることが出来ます。
・遺言者の死亡後に、相続人等が遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けたときに、他の相続人等にも遺言書がある旨が通知されます(ただし、通知する相続人等を誰にするかの申請が必要です)。
デメリット
・遺言書の保管申請は本人しか行うことが出来ません。
・保管料(3,900円)が必要です。
・上下左右にある程度の空白をあけて遺言書を記載しなければなりません(データでも保管するので、見切れないようにするためです)。
自筆証書遺言書保管制度の申請の手順
自筆証書遺言書保管制度の申請は、遺言者本人が行わなければなりません。手順は以下の通りです。
①自筆証書遺言書を不備なく作成します。
②保管申請をする遺言書保管所を決めます。
(遺言者の住所地、本籍地を管轄する遺言書保管所、遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所)
③保管申請書を作成します。
④保管申請の予約をします。(遺言者本人が予約しなければなりません。)
⑤遺言保管所に行き、保管申請をします。(遺言者本人が行かなければなりません。)
必要なものは以下のとおりです。
・自筆証書遺言書
・保管申請書
・住民票の写し
・顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)
・保管手数料3,900円分の印紙
⑥保管証を受け取ります。
また、保管申請後に下記が変更になった場合は、変更の届出が必要です。
・遺言者の氏名や住所
・受遺者の氏名や住所
・遺言執行者の氏名や住所
・通知対象者の氏名や住所
一度預けた自筆証書遺言書も、保管の申請の撤回をすることが出来ます。撤回をすると、遺言書は返却されますが、その遺言書が無効となるものではありませんので、完全に無効にしたいのでしたら、新たな遺言書を作成するか、当該遺言書を破棄するかをしなければなりません。
まとめ
・多くの方が遺言書を作成していない日本において、遺言書の作成を後押しすべく、自筆証書遺言書保管制度が出来ました。この制度により、自筆証書遺言書の紛失や改ざんなどのリスクはなくなります。
・この制度を利用するか否かに関わらず、遺言書を作成したのであれば、相続人などにその旨を伝えておけば、相続時にスムーズな手続きが出来ま